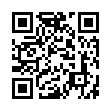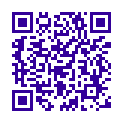アスファルトはどう使われてきたのか?
アスファルトはどう使われてきたのか?
日本の地質百選「認定」3周年記念講演会
アスファルト考古学研究の最先端

2012.5.12秋田県立博物館講堂で。
秋田県潟上市豊川油田の価値と地質学上の価値に注目し、豊川油田を近代産業遺産としての認定を勝ち取り、NPO「豊川油田をヨイショする会」を設立して、産業遺産の施設やアスファルトの露頭地の保存活動を進めているのが佐々木榮一さん。講演会当日、まず挨拶と趣旨説明。
※ ※ ※
今回5月12日行われた秋田の講演会は、「ルーフネット№95」で紹介したように、我が国の天然アスファルトやアスファルト考古学の権威が集まり、天然アスファルトゆかりの地・秋田の、県立博物館で最新の研究成果を発表するというものです。疑問解決のまたとない機会だと、思いました。
聖書の中にアスファルトが登場し、それが防水・シーリング・接着という目的のため使用された、と書かれていると言う事はわかった。では「その聖書に書かれていることは歴史的事実なのかい?」と言う疑問が出てくるのは当然でしょうね。その問題は鳥取大学の中島路可名誉教授という心強い味方が現れたので、ルーフネットはこれから一つ一つ聞いていきます。
世界史の中でアスファルト(防水材)と人類との関わりは、聖書や古代アッシリアの世界最古の叙事詩「ギルガメッシュ叙事詩」にみることができます。一方、日本では日本書紀以降、今のところ江戸時代になるまで記録が見つかっていません。
しかも日本書紀には「燃える水と燃える土を天智天皇に献上した」とあるだけで、聖書のような用途に関する詳細な記述はありません。
そこで天智天皇の時代、あるいはもっと逆上って縄文時代にはアスファルトはどんな使われ方をしていたのか。ヨーロッパの聖書時代と同じように防水・シーリング・接着という用途だったのか?という点を確かめたくなります。
講演テーマと講師
- 北海道におけるアスファルト遺物の特徴と分布
◆函館市縄文文化交流センター館長 阿部 千春 - 秋田県内の天然アスファルト使用例とその遺物特性
―烏野上岱遺跡と漆下遺跡など―
◆元秋田県教育庁文化財保護室長 大野 憲司 - アスファルト考古学の創始者「佐藤傳蔵」
◆(財)北海道北方博物館交流協会常務理事 野村 崇 - 「豊川のタールピット」
◆秋田県立博物館 副主幹 大森 浩 - 豊川油田の天然アスファルト産状とアスファルト利用の近代産業史
◆NPO「豊川をヨイショする会」理事長 佐々木 榮一
「豊川油田地域の天然アスファルトの産状とアスファルト利用の近代産業史」
それぞれの内容は順次紹介します。
約5,000年~3,000年前の縄文時代に天然アスファルトの利用は北海道から東日本全体に広がり、当時は非常に貴重な物流品でした。そして、そのアスファルトの重要な供給地の1つが豊川油田(槻木遺跡群)と考えられています。
講演ではアスファルト遺物の考古学研究を行う専門家が、北海道と秋田県内に広がるアスファルト遺物の様々な特徴について最近の知見を交え、分かり易く話しをしました。
2012/05/15(火) 18:00:53|考古・地学|