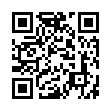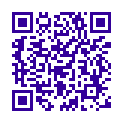武相荘講座で「未来の建築~茅葺き屋根の魅力」を語る
武相荘講座で「未来の建築~茅葺き屋根の魅力」を語る
中野誠 茅葺き職人として、24年間の経験と思いを語る
なぜ白洲邸は茅葺きなのか?

武相荘の庭で竹の切れ端を拾い、ポインター代わりに使っている。
10月25日(日)、東京都町田市・鶴川の(武相荘)旧白洲邸で、京都・美山の茅葺き職人、中野誠さんが、茅葺き屋根の魅力を語った。
中野さんは1968年、京都府南丹南市美山町北に、3人兄弟の末っ子として生まれる。父は左官業。農協職員を経て23歳で茅葺き職人に弟子入り。30歳で独立、2007年美山茅葺き㈱設立、現在に至る。多くの若い職人を育て、全国の文化財の茅葺きに携わっている。

7年前に中野さんが葺き替えた武相荘の母屋。白洲次郎・正子の暮らしの様子がそのまま残されたギャラリー。

茅葺きの構造、英国の茅葺き、合理性、土や農業との繋がり、古民家再生、伊勢神宮の茅葺きなどに関するスライドと豊富な経験談で、茅葺きの魅力を語った。
古い茅は最高の肥料で、良いコメができる。屋根に葺かれていた古い茅を利用した循環型米つくりにもとりくんでいる中野さんは、講演を次のように締めくくった。
今思うこと。
確実に「未来は懐かしいもの」であると考えます。
茅葺き=伊勢神宮より分かると思いますが、永遠に残さなければならないもの。
永遠性=自然に生えてくるススキを使い、自然にかえる。未来に全く「ツケ」を残さない。
人もまた同じ。
古来の生きた芸術。幸せの象徴。
このことを、白洲次郎・正子のお二人は、あの時代にきっと気付いていた。そう確信します。
先人より伝えられてきた歴史に敬意をはらい、学び、伝えていきたい。

武相荘は1年前のリニューアルで、駐車場をはじめ、レストラン、カフェ、バーなどの施設が整った。写真は吉田茂の片腕として戦後処理にあたった白洲次郎の資料展示室。バー&ギャラリーとして生まれ変わり、レストランから酒と料理が運ばれる。
2015/10/26(月) 06:02:09|茅葺き文化|