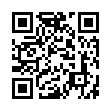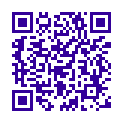行ってきま~す。近江神宮燃水祭
行ってきま~す。近江神宮燃水祭
本日、「7月7日燃水祭斎行」防水業界からも初参加します
近江神宮公式ホームページhttp://oumijingu.org/にこう書かれています。
日本最初の石油の記録は、1340年をさかのぼる、天智天皇の御代のことした。正月3日、新都大津宮において、御即位の式典を厳修せられた天智天皇7年(668年)の7月のことでした。
越の国 燃ゆる土 燃ゆる水をたてまつる
日本書紀はこう書き記しています。燃ゆる土『燃土』とは天然アスファルトのことであり、『燃水』とは石油のことです。『越の国』は、現在の新潟県。なかでも現在の胎内市(旧黒川村)であったといわれます。黒川村は、昔、川の流れが黒くなるほど燃水が湧き出したことから、「黒川」の地名がついたと伝えられています。
その7月、越の国より採掘された燃水と燃土が天智天皇の都に献上されたのでした。科学技術を駆使され国づくりを推進された改新政治を象徴する記事といえます。
黒川村をはじめ新潟県内では昭和30年代に至るまで露天掘りの油田で採油が行われ、燃料として使われてきました。
燃 水 祭 7月7日斎行 黒川臭水(くそうず)を献納する新潟県胎内市代表者。ランプを持って献灯するのは各府県石油商業組合代表者。
本年は各元売り会社の代表者が奉仕します。
毎年7月1日、新潟県胎内市黒川において燃水祭が行われ、その折採油された原油が、6日後の7日、近江大津宮旧跡に鎮座する近江神宮燃水祭において、黒川からの使者により燃水献上の儀が、往時のままに厳修されています。さながら日本書紀の記述を再現するがごとくに。
地球温暖化問題がクローズアップされるなか、化石燃料のマイナス面が強調されることが多くなってきましたが、東日本大震災にともなう原子力発電所の事故以来脱原発への志向が高まり、さりとてただちに自然エネルギー中心に転換するのは現実的ではありません。現代文明を前提とする以上、当面は石油を中心とする化石燃料に頼らざるを得ません。むしろ従来にもまして重要となってきます。
全国石油・エネルギー業界・関連業界関係者多数のご参列の中、石油業界の代表者の手により、ランプに灯をともして献灯の儀を行い、現代文明の基盤である石油への感謝の誠を捧げます。
注:燃える土=アスファルト、と記されています。
※ ※ ※

こうして、燃える水を7月1日採油し、

使者に託し、

燃える土=アスファルトとともに、460キロ先の近江神宮に、今日7月7日奉献します。(小堀靹音(ともと)の「燃土燃水献上図」はこの行列を描いたものです)
2011/07/07(木) 07:07:07|ARCHIVES|